●『顔のない眼』『デッドマン』『ブレードランナー 最終版』
最近、映画館でもDVDでも全然映画を観てなかった。最後に観たのが昨年8月の『ホット・ファズ』だもんなあ(あれは良くできていたけど、ラストがイマイチだった)。つーことで、1月下旬、半額セール中のTSUTAYAに駆け込んで借りた何本かについて。

まずはジョルジュ・フランジュ監督『顔のない眼』。1950年代末のフランス・イタリアで作られた残酷劇(いわゆる「グラン・ギニョール的映画」ですか)の古典的名作。不慮の事故で顔の皮膚を失ってしまった娘を持つ1人の高名な外科医。彼は幾人もの若い女をさらっては、その顔の皮を剥いで顔面再生の実験を繰り返していた。そしてある時、ついに移植手術は成功し、娘は美しさを取り戻したように思えたのだが……。
隅々まで「残酷」の2文字が行き渡った映画である。何の落ち度もない哀れな犠牲者、善良な刑事たちの役立たずぶり、一旦は目的を果たしたかに見えた主人公たちがあっという間にどん底に突き落とされる展開、そして一寸も救いのない結末。描写的にも、女性の顔の皮をはぐ様子をモロに映した手術場面(「まさか映すまい」と油断してたので驚いた)や娘の顔が醜く崩れていく連続写真など、思わず眼を背けたくなるシーンがいくつも挿入されている。
この作品の特長は、そうしたむごい物語や描写にも関わらず、情緒的、あるいは過激になりすぎず、突き放した冷徹な視点を貫いているところ。「肝心の場面」は静かに淡々と描かれ、登場人物は何を考えているかわからない者ばかり。主人公の医師の目的は「娘のため」なのか「実験」なのかがはっきりしないし、娘の感情もマスクで覆われて遮断されたまま。観客は誰にも感情移入できず、右往左往するばかりである。キューブリック的「神の視点」というか。
で、そこまででも個人的にはシビれるところだが、さらに良かったのは終わり方。医師が自らの行いの報いを受ける一方で、娘が1人踊りながら森に消えていく幻想的なラストシーンはとても印象的だった。この場面があったからこそ、見終わった後に単なる悲しさや恐怖とは違った、えもいわれぬ余韻と感情が残るのである。「わかりやすさ」など脇に置き、普通の映画にはない「奇妙な味」を残すからこそ、この映画はカルト的名作となり得たのだろう。
つーか、『インフェルノ 蹂躙』のラストの元ネタはこの映画だったんだな(笑)。
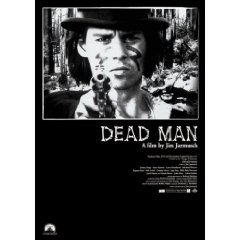
2本目はジム・ジャームッシュ監督『デッドマン』。会計士の仕事を求めて辺境の街にやってきた主人公ウィリアム・ブレイク(ジョニー・デップ)が、痴情のもつれから人殺しをしてしまいお尋ね者に。ブレイクは胸に重傷を負いながら、たまたま高名な詩人と同名だったことから「ノーバディ」という名のネイティブ・アメリカンに命を救われ、彼とともに大自然の中、追っ手から逃れる長旅を続けていく。そして、いつの間にか本当の白人殺しに……。
パッケージのカッコよさに惹かれて借りたんだけど、全然ダメな類の映画だった。
衣装やセットの作り込みは凄いし画も凝っているので、映像はきれい。でも、映像美重視の監督にありがちな事かもしれないが、演出や展開が冗長というか冗漫というか……そのくせ1カットごとにいちいち画面が暗くなって流れがギクシャクしているし。おまけにコミカルな演出と残酷・シリアスなシーンの混在が悪い方に出ていて、どうにも居心地の悪い気分がずっと続くのであった。あと、いくら男前とはいえ、デップのアップがちと多すぎるかな(笑)。
なんつーか、うわべばかり飾って中身がないという意味では、中野裕之監督の作品を思い出させるものがあった(というより、中野監督の『SF』とかはここからインスパイアされたっぽい)。Wikipediaなんかを見ると、どうも全編にブレイク(詩人の方)作品からの引用が散りばめられてる(そしてストーリー自体がブレイクの人生にオマージュを捧げている)らしいので、そこの知識がないと理解できないということなんだろうか。なんだかなーという感じ。
冒頭の汽車の場面で出てきた危ない目つきの機関士がイイな、と思ってたら、彼はカナザワ映画祭に激ヤバ作品を持ち込んだクリスピン・グローヴァーだったんだね。なるほど(笑)。

3本目は、リドリー・スコット監督『ディレクターズカット ブレードランナー 最終版』。言わずと知れたフィリップ・K・ディック原作、ハリソン・フォード主演のSFサスペンス大作。
子供の頃に劇場公開版を観た時は、正直あまり面白いとは思えなかった。アクションはパッとせず、出てくる日本人や日本語はヘンテコで、とってつけたようなハッピーエンドも不自然だった。でも、今になって観直してみると全然印象が違う。やっぱり傑作だわこれ。数年前にディックの原作小説を読んだ事が影響しているのかもしれないし、僕もオッサンになって即物的な刺激よりも表現や物語の構造にこだわるようになったからなのかもしれない。
今回観ていて気づいたのは、「意外と原作のモチーフを生かしているんだな」ということ。しみったれた惨めな未来で、生の意味を求めてあがき続ける人間とレプリカントたち。きっと20年前の僕にはその構図さえ理解できなかったのだろう。以前は原作の侘びしい感じがより好ましいと思っていたけど、映画版の重厚さ・荘厳さも捨てがたい。バッティ(ルドガー・ハウアー)が涙を流しながら死ぬクライマックスは、神々しささえ感じさせる名場面である。
劇場版と比べて改変されているラストについては、断然ディレクターズカット版の方が良いと思う。謎めいた確信の表情で一角獣の折り紙を握りしめるハリソン・フォードは、とても素敵。観客の想像の余地を奪ってしまう「わかりやすさ」なんてくそくらえだ(完全に意味不明でも困っちゃうんだけどね)!!ただし、デッカードは普通に「人間」でいいじゃないの(笑)。
しかし、この作品が作られたのが1982年……27年前か。今や、当時設定された「近未来」=2019年の方がずっと近いんだもんね。『2001年宇宙の旅』なんかでもそうだけど、本当の名作SFは時代を超えて決して古びることがない、と。
