●『イースタン・プロミス』
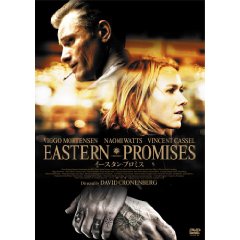
WOWOWの録画で、デヴィット・クローネンバーグ監督『イースタン・プロミス』。ロンドンのとある病院で働く助産師のアンナ(ナオミ・ワッツ)のもとに、身元不明のロシア人少女が運び込まれ、赤ん坊を残して死亡する。アンナは少女の日記を手掛かりに身元をたどろうとするが、日記にはロシアン・マフィアの秘密が記されていた。知らず知らずのうちに恐ろしいマフィアの縄張りへ足を踏み入れてしまったアンナの前に謎めいた男(ヴィゴ・モーテンセン)が現れ……。
とてもよくできた映画。達者な役者陣、謎めいた筋立てをうまくさばきながら適度に情緒を織り交ぜた脚本、巧みなサスペンスの演出、美麗な映像……etc。いや、何しろクローネンバーグ監督なので、いつズルズルグチョグチョになったり(『ヴィデオドローム』『イグジステンズ』)狂気と妄想に踏み込んだり(『クラッシュ』『スパイダー』)するかと気が気でなかったのだけれど(笑)、そんな心配は不要だった。ため息が出るくらいにバランスの良い作品だと思った。
もっとも、それでもクローネンバーグっぽさというのは消せないもので、例えば殺人や死体の描写の身も蓋もなさとか、影や闇の部分も含めて妙に映像がくっきりしているところとかは、フィーリングの領域ではあるが「ああ、やっぱり」という感じでもあった。18禁指定を受けるほど暴力描写が激しいとも思わないけど、映倫の審査員もそこら辺に妙な先入観があったのかもしれない。普通に観れば「ヤバイ話」というよりは「いい話」だと思うのだがなあ……。
あともう一つあらためて思ったのは、(特に映像面で)妙なディテールにこだわる一方で、物語や描写の余計な部分を徹底してそぎ落とすのがクローネンバーグ流ということ。とにかく無駄がなく物語が停滞することがないし、結果として多くの作品で上映時間が短くなっている(だいたい100分以内)。ラストシーンもこれ以上はないくらい最低限のところで切ってるし。おそらく「映画とは現実の一部を切り取るもの」でしかない、という確かな認識があるのだろう。
マフィアの中でのし上がっていく謎の全身刺青男ニコライを演じたモーテンセンは好演、というか役にはまりまくり。途中で彼の正体はなんとなくわかってしまうのだが、他の役者が演じていたらもっとずっと嘘くさかったろうな。もう一人の主人公ナオミ・ワッツは相変わらず美人、というかすげー好みなんだけど(笑)。ラストのキスシーンは(その手の場面が苦手な僕でも)グッと来るような絶妙な加減だったねえ。「わかる、わかるよその感じ……」みたいな。
あ、サウナでモーテンセンが刺客に襲撃される場面は凄かった。全裸(つーかフルチン)で刃物を持った相手と戦うということがいかに視覚的に「痛い」ことであるかという。結局撃退には成功するんだけど、途中手やら腹やら背中やらあちこち斬りつけられて……うーん、そう考えるとやっぱりクローネンバーグだな(笑)。
[付記]
書き終わってから気づいたのだが、マフィアの幹部の息子キリル(ヴァンサン・カッセル)がどうもニコライにも隠れゲイ的な親愛を抱いているように描写してあるあたりも、クローネンバーグっぽいっちゃぽいのかもしれない。『戦慄の絆』『裸のランチ』『M・バタフライ』『クラッシュ』……初期の傑作『シーバース』の結末、寄生虫に乗っ取られてフリーセックスに狂った人々が主人公に群がる場面も、そういやあ男性・女性関係なかったような。うーむ。
