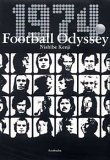●『1974 フットボールオデッセイ』
西部謙司著『1974 フットボールオデッセイ』(双葉社)読了。今やサッカーの歴史において伝説となった感のある、74年W杯決勝西ドイツ×オランダ戦。その試合で対決した両チームの「スター」たちの人となりや経歴を、色々な意味で転回点を迎えていた当時のサッカー界の状況にも言及しつつ、小説の形式をとってドラマティックに描き出した本である。
読んだ感想は、とにかく「面白かった」の一言に尽きる。筆者曰く「起こった出来事については、ほぼ事実」「人物造型に関しては9割方フィクション」だそうだが、主要人物の振る舞いや言動はいかにもそれらしく、生き生きと「作られている」。もちろん、小説であるがゆえに描写の臨場感(特に決勝の序盤と主人公格フォクツの登場時!)はノンフィクションとは比べものにならない。エンターテイメントとして、非常に高いレベルの一冊に仕上がっている。
まあ、事実と異なる(かもしれない)脚色と言ってしまえばそれまでで、選手たちの内なる思いや試合中の会話なんて、創造(あるいは想像)の産物としか言いようがないわな。ただ、フォクツ=「闘志の塊」、クライフ=「カミソリ型の天才」、バイスバイラー=「最高に頼れるオッサン」といった人物造型や、下手くそリフティングでゴールポストを壊すフォクツといったエピソードの数々には、古いファンも「あー、そうだそうだ」と頷きそうな気がするのだが。
そもそも、そうした脚色の題材となる事自体が、当時のスターたちがいかに個性的であったかという証左でもあるのだ。フォクツ、ネッツァー、バイスバイラー、クライフ、ベッケンバウアー、etc……。今と比べるのは難しいけど、少なくともこれだけ規格外の選手や指導者が活躍していた70年代欧州は「豊かな時代」だったのだろう。西部さんもノリノリで書いた様子で、バイスバイラーの訛り(「~かえ?」って、「0-0」かよ(笑))など、行きすぎた描写もとても楽しい。
特に印象に残ったのは、ベッケンバウアーの野獣性と、フォクツが試合中ふざけた喋りでマーク相手を苛つかせる場面だろうか。ベッケンバウアーについては先日W杯中に「21も年の離れた女性と3度目の結婚」「5人目の子供の誕生間近」という話に驚いたばかりだが、この本を読んで納得。「夜も皇帝」ってか(笑)。フォクツの方は、00年のJ1開幕戦で小池が俊輔を粘着マークした時の話を思い出した。「うまいねー!キミ、名前なんて言うの?」(笑)。
と、そんな感じの佳作なのだが、一つ難癖をつけるとすれば、逸話の集積に走りすぎて「なぜ74年W杯の決勝が伝説なのか」という部分(筆者の言うところの「天下分け目」性)を語り切れていないところか。トータル・フットボールの意義を説明するくだりはあるし、出場選手が凄い連中だというのは良くわかるんだけど、「なぜこの試合が」という部分については舌足らずかも。まあ、これだけの「物語」を紡ぐきっかけになった試合だから、ということなのかな。
ともあれ、僕のような「80年代半ば以降の」サッカーファンにとっても十分に楽しめる本であるのは間違いない。センチメンタルな物語を楽しみたい人にも、当時のサッカーを「勉強」したい人にも、フォクツに小峯やペルーを重ねて懐かしみたいオッサン東京ファンにも(笑)、ぜひお薦めしたい一冊。